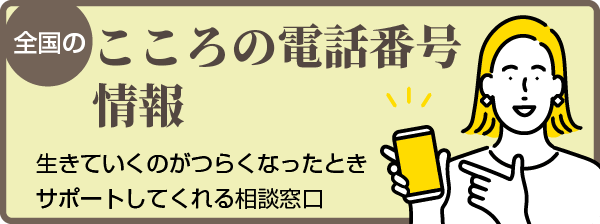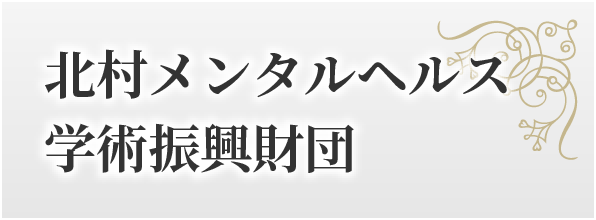メンタルヘルスを見てみよう
株式会社北村メンタルヘルス研究所は
文部科学省科学研究費助成事業指定研究機関です。
最高管理責任者および不正等の相談窓口はこちらへ ⇒ info@institute-of-mental-health.jp
トピックス
- 2025.4.4
- 北村メンタルヘルス研究所 youtube チャンネル始めました。
チャンネル登録よろしくお願いします。
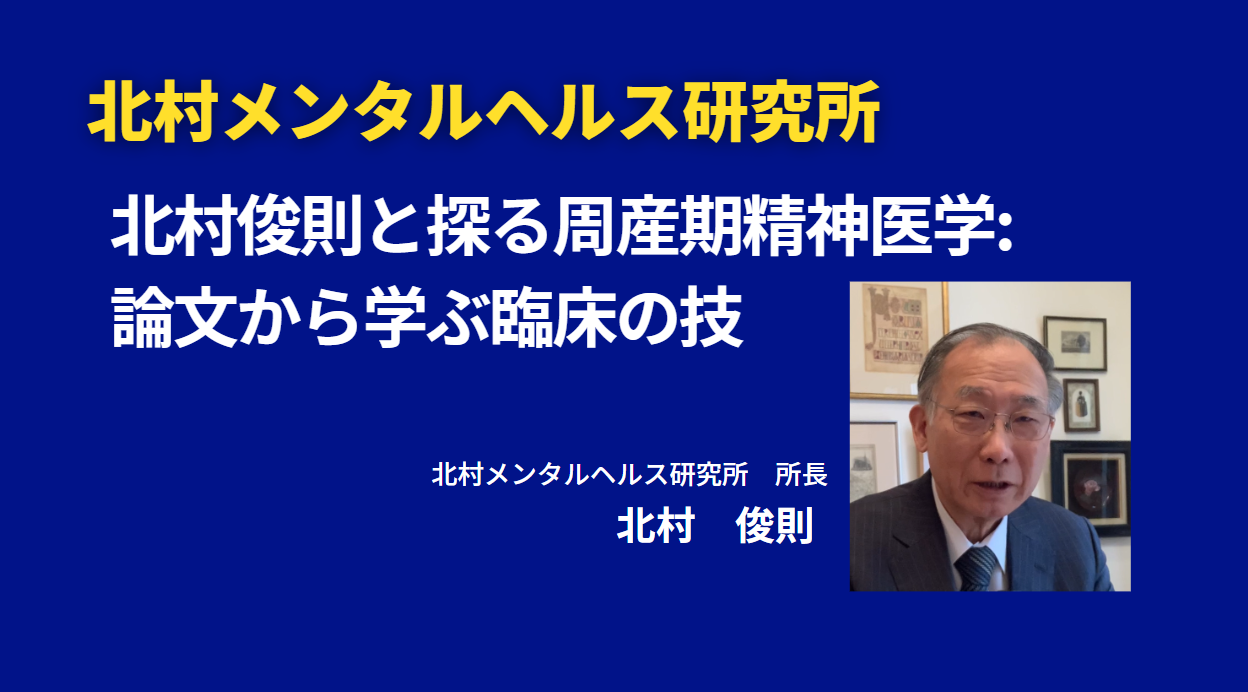
- 2024.7.20
- 「ボンディングとその障害」を更新しました。
- 2024.6.1
- 「メンタルヘルスに特化した産前・産後ケアハウス」を令和6年度都民提案に応募しました。
都民提案は「都民が提案し、都民が選ぶ」事業提案制度です。
7月下旬から8月下旬まで、都民によるネット投票で決定されます。提案の詳細は ⇒PDF - 2024.6.1
- X 北村メンタルヘルス研究所はじめました

- 2024.4.15
- 下記の論文で出産恐怖の診断基準の提案を行いました。
Kitamura, T. et al. (2024). Tokophobia: Psychopathology and diagnostic consideration of ten cases. Healthcare, 12, 519. - 2022.3.15
- 日本評論社より『ボンディング障害支援ガイドブック:周産期メンタルヘルス援助者のために』が刊行されました。
- 2021.6.24
- ボンディングとその障害の資料を更新しました。
- 2021.5.8
- 北村メンタルヘルス研究所倫理審査委員会の内容を更新しました。
- 2020.12
- 日本評論社より『子どもを愛せないとき:ボンディング障害を知っていますか』が刊行されました。
- 2019.10.23
- 「産後うつ病・児童虐待・嬰児殺に関する意見」と「ボンディングとその障害」を更新しました。
- 2018.9.10
- 「ボンディングとその障害」を更新しました。
- 2018.9.1
- 「ボンディングとその障害」を更新しました。
- 2018.9.1
- 倫理審査課題一覧を更新しました。
- 2018.7.6
- 北村メンタルヘルス学術振興財団主催の第5回周産期メンタルヘルスセミナーの詳細が決まりました。「周産期ボンディングとボンディング障害:エビデンスと課題」というタイトルで、2018年11月11日に社会福祉法人聖母会聖母病院5階講義室(西武新宿線下落合,西武池袋線椎名町)にて開催されます。
詳細は ⇒ http://www.kitamura-foundation.org/seminar.html - 2018.6.27
-
2018年5月24日25日の両日、スタフォード(英国)で Stafford Symposium が開催され、12か国から60人ほどの参加者があり、周産期精神医学に関する発表が行なわれました。主催は Professor Ian Brockington (バーミンガム大学名誉教授)。主たるテーマはスタフォード面接(第1日目)とボンディング障害(第2日目)でした。北村が日本におけるボンディング障害研究の最新情報を報告しました。

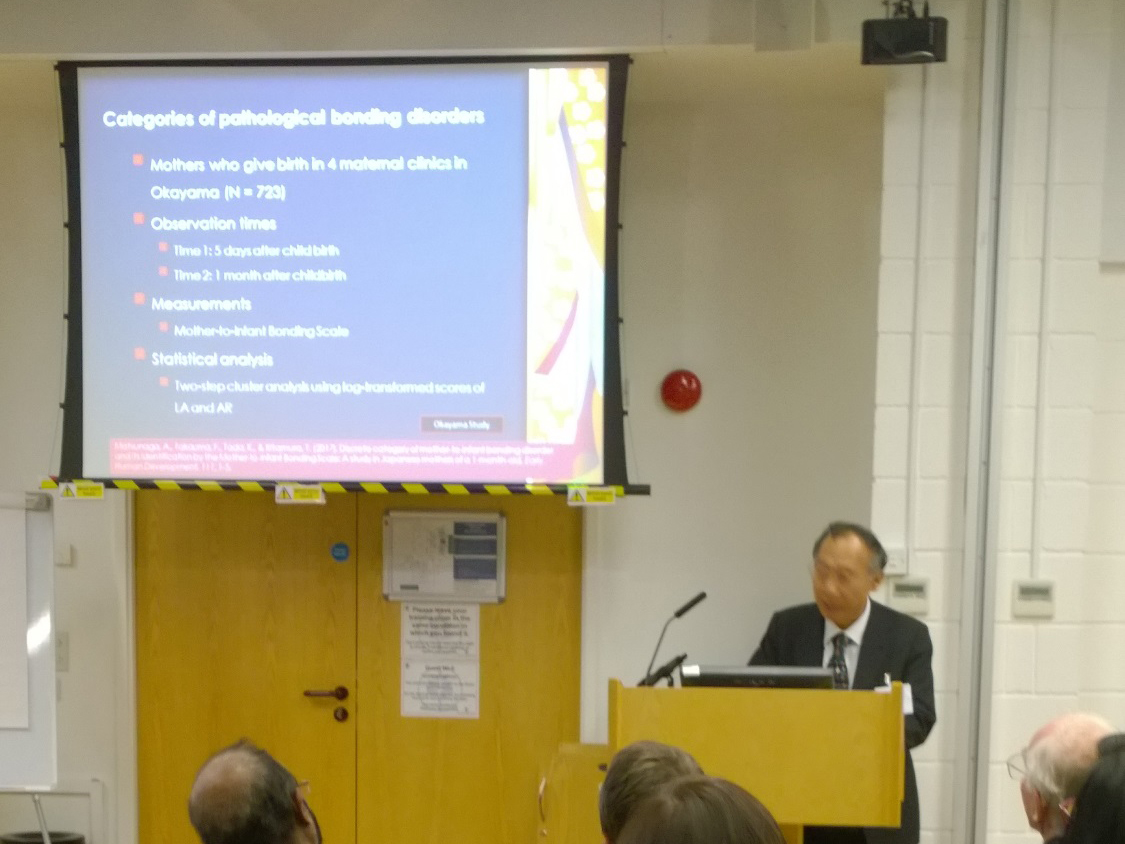
発表風景

パネルディスカッション
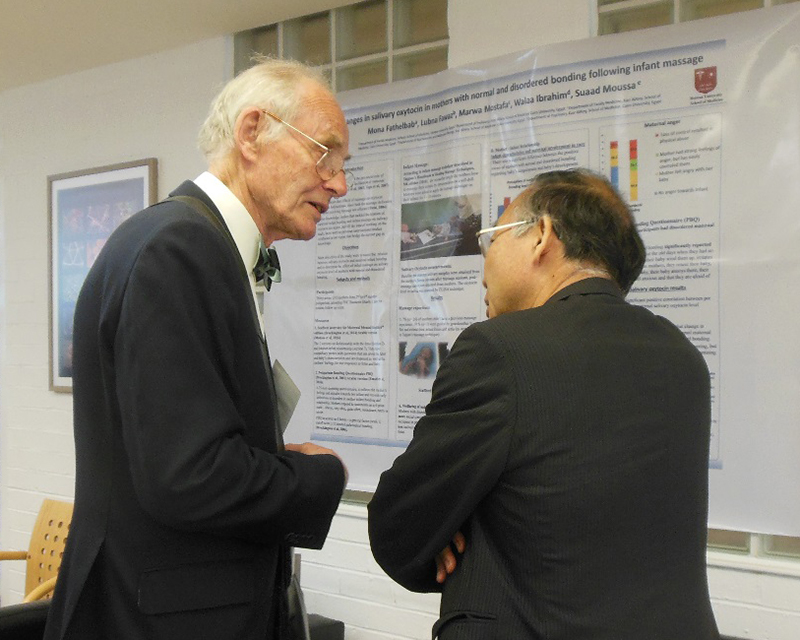
Prof Ian Brockington と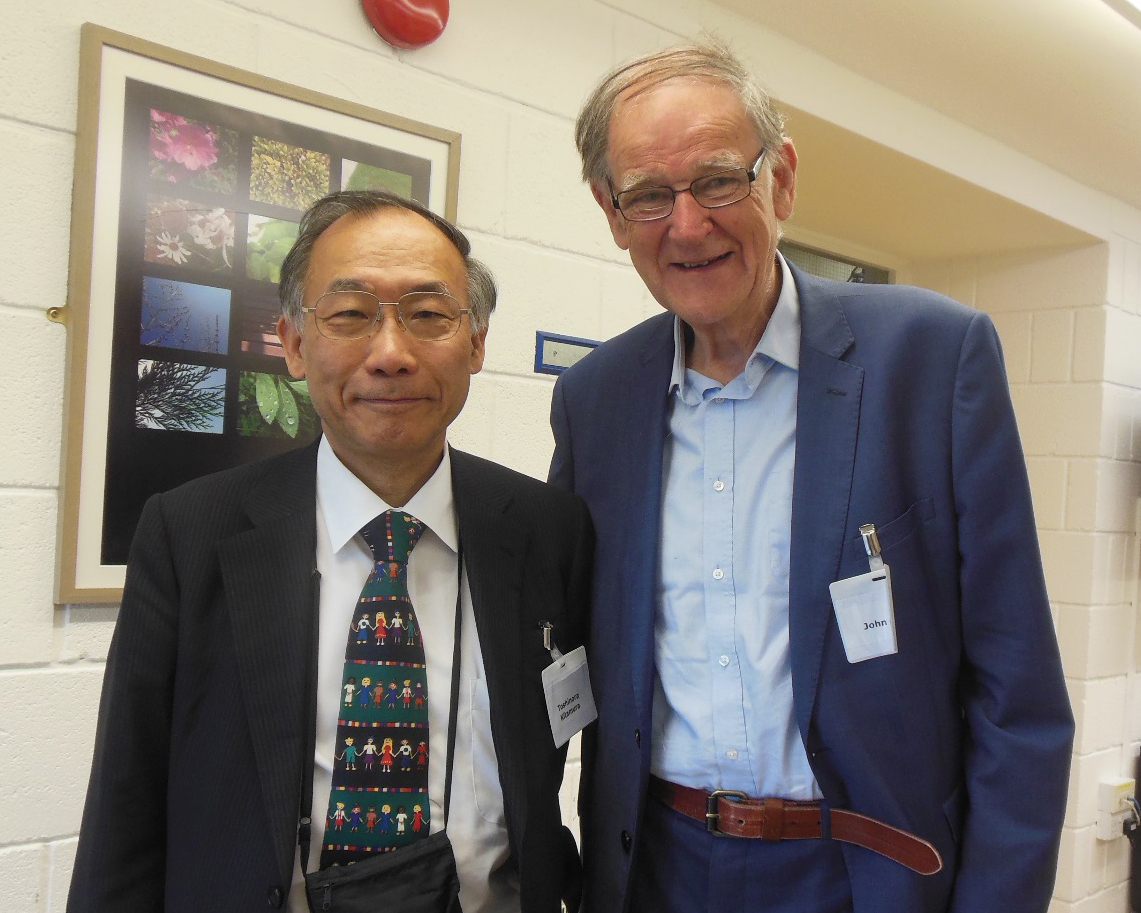
Prof John Cox と
懇親会

Prof Brockington ご夫妻と
スタフォードの風景 - 2018.4.5
-
2018.3.4. 認定NPO法人フロ-レンス主催の「夫婦のための特別養子縁組研修:実践編」が、2018年3月4日に飯田橋グラン・ブルーム3階会議室で15組の養子縁組里親希望のご夫妻の参加をいただき開催されました。北村メンタルヘルス研究所からは北村に加え、4名の研究員がグループセッションのファシリテータとして参加しました。

また、この時の様子や、養子縁組の実情が Youtubeにアップされています。ご興味があれば、ぜひご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=9eSRCIB8CaQ - 2018.3.6
-
「精神に疾患は存在するか」に書評をいただきました。
精神に疾患は存在するか
北村俊則著
星和書店、A5判296項、2,700円(税込2,970円)、2017年6月刊
(学習院大学)滝川 一廣
「精神療法」第44巻第1号 pp.120 - 121.
チャレンジングな書名である。書名からピンとくるものがあって早速読み始めたが、期待どおりの内容だった。私は不勉強で、これまで著者を存知上げず、そのお仕事も本書で初めて知った。そのため、以下は私の想像まじりの感想と批評となるのをお許し願えたらと思う 略歴によれば著者は1972年に医学部を卒業し、そのまま精神科医となられている。私は75年卒で3年後輩となるが、ほぼ同じ時代の空気のなかで精神医学の道を歩み、だから著者の問題意識はわがことのようにわかる。70年代に精神医学には、60年代に燃え上がった「反精神医学」(精神障害をすべて患者個人の心理や脳の問題に帰責し、医学の名のもとに社会的排除を助長してきたとする旧来の精神医学への異議申し立ての運動)の残り火があった。また、大学のアカデミックな権威主義や閉鎖性を否定・解体せんとした大学紛争(医学部から始まった)の余波もあり、既成の権威にとらわれず自由に学ぼうとする雰囲気が研修医の間にあった気がする。 そこで駆け出しの精神科医が患者を前にぶつかったのは、医学生時代に「これが医学だ」と学んできた身体医学ベースの「近代医学」のコンセプトへの疑問だった。それが果たしてどこまで不偏性をもつのか、精神医学においても十分な適合性や妥当性をもつのかという問題である。反精神医学がラディカルなかたちで提起した問いに重なるところがあり、この本が反精神医学から書き起こされているのは当然といえる。精神において正常とは何か異常とは何か、それは分かたれうるものなのか、なにを「治す」ことが精神科治療なのか、自分たちはなにを根拠にある精神現象を「疾患」と捉えることが許されるのか、そもそも精神に「疾患」はあるのか…こうした問いに考え込んだり、同僚や先輩と論議したりといった経験から出発した精神科医は当時少なくなかったと思う(いまもそうだろうか)。
その後の歩みは各人様々で、そうした「青臭い?」問いはこころの隅にそっとしまって実務的に診療に打ち込む実地医家の道をたどる者が多かっただろう。もうひとつは、精神医学を可及的に身体医学に引き寄せる(引き寄せられない部分は切り捨てる)方向へ舵を切ることによって「医学」であろうとする道だった。学術研究を目指す人たちの多くがこの道を進み、今日の生物学的精神医学はその到達である。
しかし、著者はどちらにはいかず、初めにであった問いを手放さず、まさに自身のテーマとする道を歩んだ数少ない精神医学者ではないかと思う。精神病院勤務の後、著者は英国に学ぶ。英国は、反精神医学の旗手で治療共同体を実践したR・D・レインの地であり、同時に堅実な実証主義の伝統をもつ国である。反精神医学が大事な問題提起をしながらやがて退潮した理由のひとつは、その異議申し立ては的を射ていたものの、ではどうすべきかにおいて理念に傾き過ぎたところにあったと考えられる。省みれば、先に挙げた問いやそれを巡る同僚先輩との議論も、ややもすれば観念的なものに終わりやすかった。やがてこころの隅にしまいこまれたり、精神医学の身体的医学化に取って代われたのは、そのせいかもしれない。ところが、著者の取り組みはそれとは違っている。
目次のとおり、「第2章 連続的分布傾向を示す生命現象は病理的か?」「第3章 精神疾患は社会的に不適応か?」「第4章 統計的少数が精神疾患か?」「第5章 精神科診断が偏見を誘導するか?」など多角的にリサーチクエスチョンが立てられ、論考の柱となっている。そして、それぞれについて具体的な調査データや統計学に基づく実証的な検討が多岐にわたって試みられ、その積み重ねが書名の問いへの著者の答えとなる。操作的診断と生物主義とに大きく偏った現代精神医学への危惧を内に秘めているが、それを声高な理念によってではなく、実証的事実に語らせんとするのが著者の姿勢である。
では、精神医学は本当はどうあるべきか。これについても著者は控えめに、しかし急所を述べている。「従来精神疾患と呼ばれてきたさまざまな心理状態は、その個体と個体が置かれた対人環境の間の相互作用の産物なのです」「対人関係の評価が、精神医療のなかで重要なものとなります」「関係性の評価は精神科診断学の将来の重要課題です」等々。かつてH・S・サリバンが「精神医学とは対人関係論である」としたのに相通じるものにちがいない。このテーマは「別の機会に細かく検討したい」と著書は述べている。その機会をこころ待ちにしたい。
- 2018.3.6
-
気質と性格研究の TIC and mental and personality disordersを更新しました。
→ 過去のトピックスはこちらから